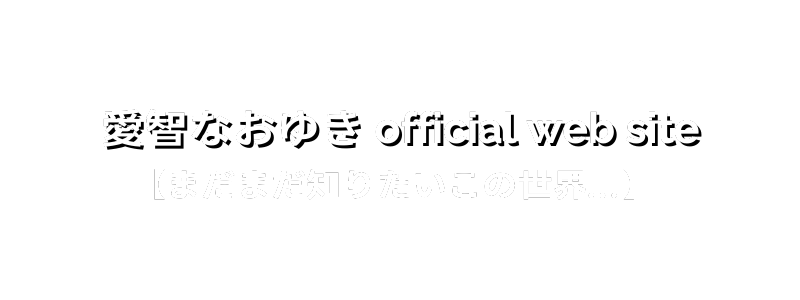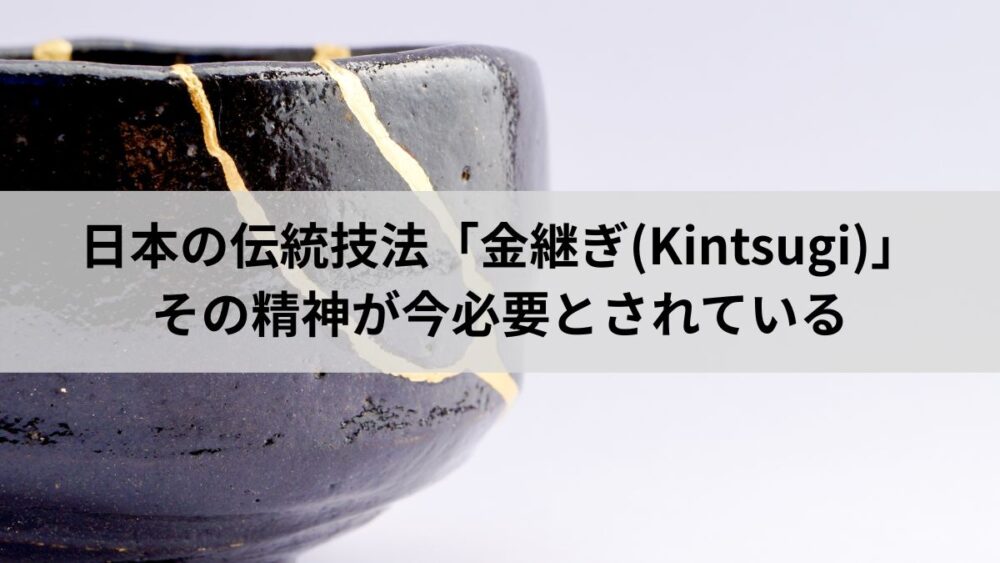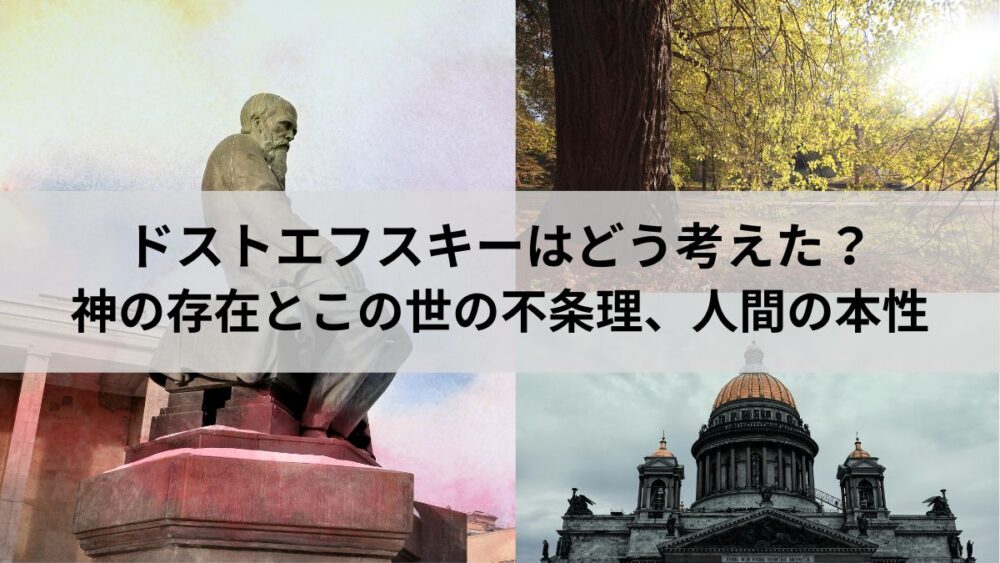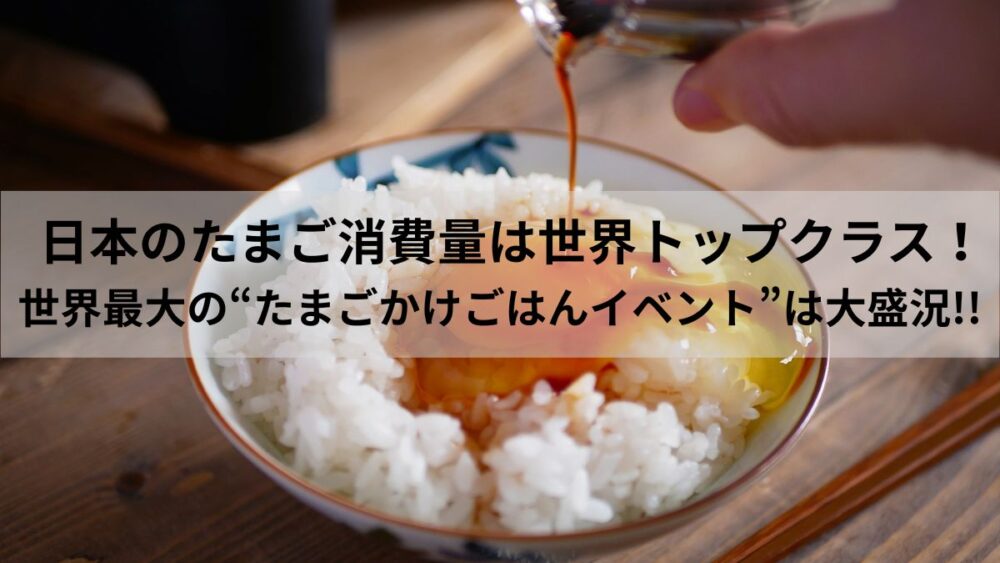壊れてしまった磁器や陶器を自然の素材で修復する日本の伝統技法「金継ぎ(きんつぎ)」。その歴史をたどると、なんと縄文時代にまで遡るというから驚きです。
先日の2025年9月11日~15日、東京は御茶ノ水ソラシティにて、「金継ぎ」によって修復された作品が展示される「金継ぎ作品展」が開催されました。
(イベント開催概要:https://kintsugi-girl.com/exhibition2025/)
主催者は、金継ぎによる修理や金継ぎキットの販売、その他、金継ぎ教室やワークショップなどを行っている「株式会社つぐつぐ」。
こちらの金継ぎ教室の講師とそこで学んだ生徒の方たちが、その成果を発表する場となっているのがこの「つぐつぐ金継ぎ作品展」。今回で2回目の開催となりました。
筆者はこの「金継ぎ」で修復された実物を間近に見たことがなかったため、この展示会にはぜひ行きたいと思い、この度見学にうかがいました。
なお、当展示会における写真撮影や本ブログへの掲載に関しましては、株式会社つぐつぐの代表取締役の方から快く許可をいただきました。この場を借りて改めてお礼を申し上げます。

「金継ぎ」とは?その基本的な工程を紹介
「金継ぎ(きんつぎ)」についてあまりご存じない方のために、「金継ぎ」とは何か、改めて記載をしておきます。
「金継ぎ」とは、漆(うるし)などの自然の材料を使って、破損した陶磁器を修復する日本の伝統的修理技法のことをいいます。
漆は、ウルシ科ウルシ属の木から採取した樹液のことで、空気にさらされるとゆっくりと硬化する性質があるため、塗料や接着剤として利用することができるのです。
その「金継ぎ」の基本的な工程は以下の通り。
①接着 ⇒ ②大きな欠けの埋め ⇒ ③小さな凹凸の埋め ⇒ ④中塗り ⇒ ⑤仕上げ
(②~④は完全に平らになるまで何度も繰り返す)

そして仕上げでは「金粉」をのせて、あえて修復した部分を目立たせるのがユニークなところです。
「金継ぎ」の歴史
日本において、土器や木の器などの道具を、漆を用いて修復していた歴史はかなり古く、なんと縄文時代(およそ13,000~2,300年前)の土器にも、その痕跡が見られたとのことです。
8世紀の奈良時代には、木の器などに漆で絵や模様を描き、乾かないうちに金などの金属粉を蒔いて装飾を施す「蒔絵(まきえ)」と呼ばれる技法が生み出されました。

陶磁器に対してこれらの技法が用いられたのは、15世紀室町時代。足利義政将軍が所持することとなった歴史的いわれのある貴重な青磁茶碗。この底部がひび割れていたため、中国に送ってこれに代わる茶碗を求めたところ、当時の中国にはこのような青磁茶碗は既になかったため、ひび割れた部分を鎹(かすがい/木材と木材を繋ぎとめるためのコの字形の釘)で止めて修復したものが日本に送り返されてきたといわれています(下の画像一番左)。

これを契機に陶磁器の破損箇所に「蒔絵」の技術を用い、修復を行うと同時に金粉を使って装飾を施す「金継ぎ」の技術が確立されていったと考えられています。
伝統的技法「金継ぎ」の特徴
次に、この伝統技法の「金継ぎ」と現代の簡易的金継ぎとの違いを簡単に見てみましょう。
| 伝統的技法「金継ぎ」 | 現代風(簡易)金継ぎ | |
| 安全性 | ○(食器にも安心) | ✕(食器不可) |
| 匂い | ○(乾くと無臭) | ▲(科学的な匂いが残る) |
| 主な材料 | ○(漆、その他自然の材料) | ▲(合成接着剤、エポキシパテ) |
| 修理期間 | 2~3ヶ月 | 1~10日 |
| その他 | 漆が肌に着くと、かぶれる可能性がある(要手袋) | かぶれは少ない |
| 価格 | 高い | お手頃 |
このように伝統的技法の「金継ぎ」は、一連の工程が完了すればとても「安全性」に優れるものであるということができます。
「つぐつぐ金継ぎ作品展2025」概要と出品作品
2025年9月11日~15日、東京・御茶ノ水ソラシティにて行われた「つぐつぐ金継ぎ作品展2025」。作品が展示されていた場所は、ソラシティ内にある「KS46Wallピクチャーレールゾーン」と「Gallery蔵」でした。
「KS46Wallピクチャーレールゾーン」は、ソラシティプラザからGallery蔵へと続く遊歩道に面したショーウィンドウスペース。こちらには主として、「つぐつぐ金継ぎ教室」の生徒の方たちの作品が並べられていました。
破損してしまった陶磁器へのそれぞれの「思い」がつまった作品たち。その横には、作者の一言が添えられているものもありました。


一方「Gallery蔵」には金継ぎ教室講師の作品や、明治、昭和の時代に金継ぎ師によって金継ぎされた販売品などが展示されていました。
ちなみにこちらの「Gallery蔵」は、1917年(大正6年)に書庫として建てられ、その後画廊として使われていた蔵になります。



以下の2枚の画像にある作品は、全く別の器の破片を金継ぎした作品です。


このように破損した場所を金粉などで装飾し、あえて目立たせることで、それが新たなデザインとなりそこに新たな命が吹き込まれる。損傷する前よりも美しく感じるものまであるのです。
崇高な精神文化へと昇華した「金継ぎ」
「金継ぎ」の魅力は一言では言い表せませんが、やはりその背後にある哲学や精神、長い歴史の中で育まれた「詫び寂び(わびさび)」の心が目にみえる「形」となって表現されている点、そしてそれを「現代に生きる我々も感じることができる」というところが大きな魅力の一つなのではないでしょうか。
豪華絢爛なものよりも、つつましく質素なものの中に奥深さや情緒を感じる美意識。
作為的にきれいに形作られたものよりも、不完全なものの中に「美しさ」を見出す心。
新しいものよりも年月を経たものに「美」を感じる感性。「老いる」ことを前向きに捉える考え方。
このような「詫び寂び」の精神によって、「金継ぎ」はより高尚な精神文化を伴うものへと昇華していきました。
壊れてバラバラになった器も、そこに手間暇を惜しまず心をこめて修復すれば、見事に「再生」させることができる。場合によってその美しさは、新品を凌駕するものになる。そして世の中に二つとない「Only One」の輝きを放つものになることを、私たちの目の前に示してくれるのです。
大量生産・大量消費の社会が当たり前となった現在。破損したものはすぐ廃棄して、新しいものを求めることが常識となっています。
そして長く続いた大量生産・大量消費社会の対象となるものは、いよいよ「もの」だけに留まらず、「人」に対してまでも広げられているのではないのか。
何もかもが使い捨てとなる現代社会の根底にあるその価値観は、いま修正を迫られているのではないでしょうか。
元に戻せないほど傷つくことがあるのは、器に限らず人間も同じ。
でも傷つき壊れたものにも、またやり直せる道がある。そしてそれは時に以前の姿よりも輝いて見えることがある。「金継ぎ」は私たちにそんな可能性を示してくれます。
使い捨てを当たり前とする価値観に代わり、次の時代を支える「新たな理念」となるものは、もしかすると何世紀も遡る伝統技法の「金継ぎ」の中に見出せるのではないだろうか。
その精神は日本だけに限定されるものではなく、いま世界が「必要」としているものなのではないのか。
「金継ぎ」された作品を目の前にして、そんな考えが頭に浮かびました。
「Kintsugi」は今世界で注目を集めている
上記の作品を見て分かるとおり、「金継ぎ」は単なる修復技術ではなく、芸術作品としても広く世界に受け入れられています。現代の陶芸家やクリエイターからも注目され、ますますその芸術的価値を高めているのです。
昨年の2024年にはOxfordの辞書にも「Kintsugi」という英単語が登録され、世界の共通語となりました。
そしてその伝統技法と精神は、芸術作品としての「美しさ」とともに、世界中に広がりを見せています。
その繊細な作業は集中力を要するため、ワークショップや金継ぎ教室に参加した人は「瞑想」のような感覚になることがあるといいます。「金継ぎ」の作業に夢中になる時間、それは毎日の忙しさを忘れる「癒し」の時間でもあるのです。
さらにその作業は、破損した陶磁器の破片をつなぐだけでなく、一緒に取り組んだ家族や友人、仲間との「絆」もより強くつないでくれます。
「金継ぎ」は時代を超え、現代でもなおその輝きを失わない、すばらしい伝統文化なのです。
出典及び参考資料
1) 「つぐつぐ金継ぎ作品展2025」展示資料
2) 金継ぎ – Wikipedia
3) 御茶ノ水ソラシティ