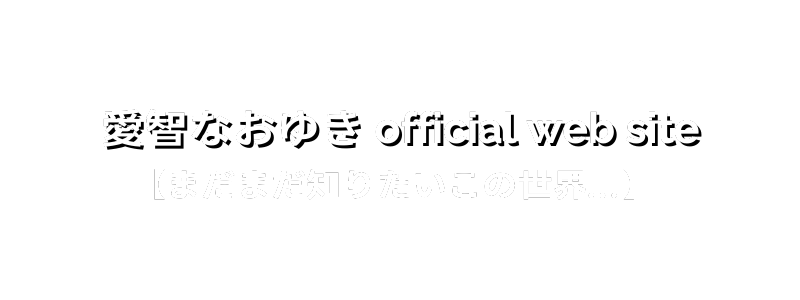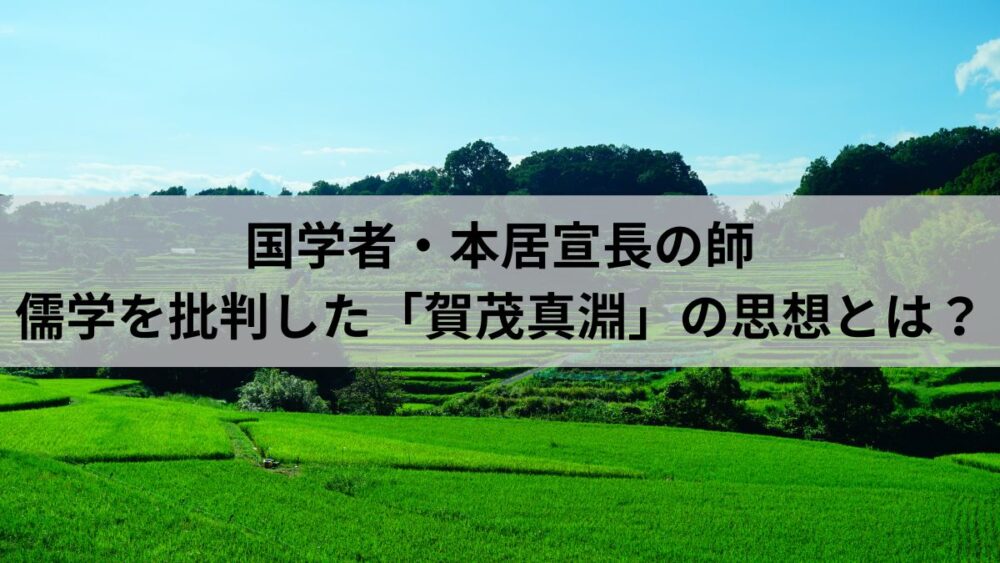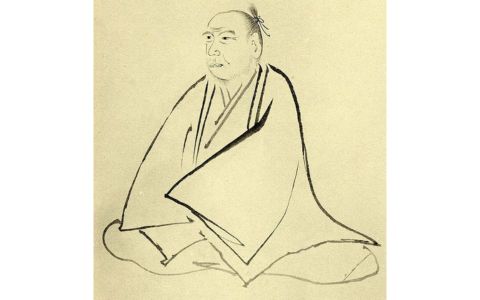江戸時代の思想家というと、※儒学者の荻生徂徠や、国学者の本居宣長などが有名だと思いますが、今回の記事では、その本居宣長の師である賀茂真淵に焦点をあて、彼がどんな主張(思想)をしていたのかを見ていきたいと思います。
(※儒学:道徳や倫理を重視した「孔子」の教え・思想を始祖として体系化された学問)
江戸時代つまり徳川幕府の時代は、戦国時代の動乱のあと武力で統治を行う武断政治で始まり、やがて教育や学問によって社会を安定かつ秩序あるものとする文治政治へと転換がなされて行きました。
このために幕府は、主君と臣下の関係を重んじる「儒学」を重視し、儒学者を登用して臣下に講義なども行うようになります。
当時の日本の知識人といえば、その多くは「この儒学をどのように解釈するのか?」ということが一つの大きなテーマであり、このことについて様々な議論が行われ、その中から現在も知られるような思想家が現れていきました。
一方、この儒学の古典(「論語」を含む四書五経など)や仏典を重視する傾向に対する一つのアンチテーゼとして、日本の古典や国史を研究し、儒教や仏教などの外来の思想の影響を受ける前の「日本独自の精神」を明らかにする学問が立ち上がっていきます。この流れがやがて「国学」という学問体系を形作ることになるのでした。
その潮流の中から、「万葉集」を研究し、国学を学問として確立した賀茂真淵が現れ、その思想が門人(弟子)である本居宣長に受け継がれていきます。
画像引用元:Wikimedia Commons 賀茂真淵 (1697-1769)
賀茂真淵の生い立ちと「生涯一度切り」の本居宣長との出会い
元禄10年(1697年)、賀茂真淵は現在の静岡県浜松市にあたる地域(遠江国)で賀茂神社の神官であった岡部家の三男として誕生しました。
賀茂真淵は10歳の頃、当時浜松市で私塾を開いていた杉浦国頭の妻、真崎から手習い(今で言う習字)を学びます。杉浦国頭は浜松諏訪大社の神主で、荷田春満を師として遠江国、三河国に国学を広めた国学者でした。
その後賀茂真淵は26歳で結婚しますが、翌年妻を亡くしてしまいます。思い合った妻との結婚生活は充実したものであったようで、歌人である賀茂真淵はそのあまりの悲しさをその後和歌にもあらわしています。
30歳を過ぎると京都に移り、杉浦国頭の師である国学者・荷田春満のもとで学ぶことになりました。元文元年(1736年)、荷田春満が亡くなったあとは一度浜松に戻りますが、翌年には江戸に移り国学を教える立場につきます。その後50歳になる頃には、徳川第8代将軍吉宗の三男であり、松平定信の実父である徳川宗武(田安宗武)に仕えることになりました。
宝暦7年(1757年)、ちょうど還暦の頃「冠辞考」を刊行。「冠辞」とは枕詞のことで、この書物は万葉集などに使われている枕詞についての解説をした辞書のようなものでした。
まだカタカナ、ひらがなが誕生する前に書かれた、日本に現存する最古の和歌集である「万葉集」は、日本語を表すために漢字の「音」を借用した「万葉仮名」という漢字が使われており、これを含めて全て漢字で表記されていました。
賀茂真淵は、それまでなかなか理解できなかったこの「万葉集」などに使われている枕詞を理解するために、それまでの後世の人間が行った解釈を排し、用いられている漢字の「意味」ではなく、当時使われていた古典言語である「大和言葉」の意味を直に考える方法を採用したのです。
賀茂真淵はこのように、それまで確立されていなかった古代日本の文書解読のための学問的手法を確立し、万葉集の冠辞(枕詞)の役割や意味を画期的に解釈することに成功して、これらの注釈を完成させました。
この「冠辞考」に触れて、あの本居宣長はその後本格的に国学に身を投じることになります。本居宣長は「冠辞考」を一度読んだだけでは全く理解できなかったようですが、繰り返し読むうちに段々その奥深さに魅かれていくのでした。
そして、賀茂真淵は60代後半になる頃に、徳川宗武の命を受けて大和国(現在の奈良県)に行くことになりますが、その際、伊勢神宮を参拝し松坂にも訪れます。この時これを聞きつけた松坂出身の本居宣長は、賀茂真淵が宿泊していた旅籠(宿泊施設)に現れ、そして「古事記」の解釈について指導を請い入門を願い出たのです。その年の終わりに入門を許可された本居宣長は、その後文通で指導を受けることになるのでした。
賀茂真淵と本居宣長が直接会ったのは、後にも先にもこの一度切り。生涯一度の出会いは「松坂の一夜」と呼ばれており、本居宣長がその後およそ35年もの年月をかけて取り組んだ「古事記」研究の集大成である「古事記伝」(「古事記」の注釈書)を生むきっかけとなる一日となったのです。
賀茂真淵の思想
前置きが長くなりましたが、それではここからいよいよ本題に入ります。
歌人でもある賀茂真淵は、前記の通り「万葉集」の研究者でした。
「万葉集」にある歌が作られた時期は、かなり幅があると考えられており、その説も諸説あるようで明確な時期を同定するのは困難なようですが、古いものでは7世紀の初期、新しいものは8世紀の中頃と考えられています。
作者は皇族や貴族などの高貴な身分の者だけでなく、中・下級の役人、また、農民や防人などの庶民が作ったものと考えられる作者不明の歌も収められています。
万葉集に収められている歌の特徴として挙げられるのは、あまり技巧にこだわらず、素朴で素直にその感情を表現しているということ。そしてそれ故にそれらの歌はとてもリズミカルで、非常に清らかで美しさが感じられるものであるということです。
これらの歌から読み取れる日本古来の精神、まだ儒教や仏教などの外来思想の影響を強く受ける前の古代日本人の心のあり方、作為がなく自然で理屈張っていないため、素直でひねくれたところがないその精神を、賀茂真淵は高く評価するのでした。
そして彼の代表的著書「国意考」の中では、以下のように具体例を挙げながら儒者の主張を批判しています。
【賀茂真淵の儒学に対する主張の要点】 (出典:国意考)
・儒者は、(※)堯、舜など、幾千年も前のことを取り上げて、その理想的な時代のことばかり賞賛するが、その後はいつの時代を見ても、現在の中国にあたる地域においては天下が理想的に治まったことがない。
(※) 堯:中国の伝説に出てくる君主。儒家にとって理想的な聖人。
舜:堯の後継者。堯と同じく徳をもって天下を治めたとされる。
・儒者たちは、現在の中国にあたる地域では儒家の教えによって十分安定した社会が作られているように言うが、その地域の実際の様子を見ればそれが単なる理想でしかないことがよく分かる。
・一方、日本は天地の心のままに治められて来たから、儒学のように美しくまとめられた理屈張ったものはなかった。日本の古の道は決して二三の人によって作られたものではなく、天地の道理に合う正しい心に沿ったものであるから、理屈張らず、和らかで、人の言葉でその全部を言い表わし難いものである。
・儒道が日本に入ってきてから、壬申の乱などの激しい内戦が起こるようになり、また奈良の宮廷では全てにおいてその表面だけを美しく取り繕うようになり、人の心が悪くなってしまった。
・儒家の教えによって、ときに君臣の間には度を越した一線が画され、人々は君に盲従するばかりで、君臣の間に親しみをもつことが出来なくなってしまった。
・現在の中国にあたる地域では、上に立つ人は自分の威光を誇示し、身分を自慢するようであるが、これは全く不可で、質素をこそ示すべきである。身分の尊いことを人々に示せば、結局国の乱れる原因となる。威を示すのは武士道以外にはない。
・医者に例えていうと、昔の中国の文章をよく読むことができる者に限って、実際に病人を治すことが少ない。我が国に自然と伝わり、理屈がよく分かっていない薬の方がかえって病気を治し易いものである。
・儒者は決して他にもよい道があることを受け入れようとはしない。儒教の学者は、理屈では優れているが、その癖実地に当たってはかえって上手くいかないものである。現在の中国にあたる地域においても政治を儒者に任せて成功しなかった場合が多かった。
・「今では古の道は全て途絶えてしまったのか」という質問を時々耳にするが、天地は永久であるのだから、これに基づいた古の道は決して絶えることはない。
・人間を鳥や獣と違った特別な存在であるというのは、人間が自己を自慢し他を侮った言葉である。天地の目からすれば、人間も鳥獣も草木も虫も同じように見えるはずである。
・結局のところ、儒道は理屈に過ぎて現実と調和しない。
このように日本古来の精神への復古を唱えた賀茂真淵の思想は、前にもある通り、本居宣長など数多くの門下生に受け継がれ、その後本居宣長の著作を読んだ平田篤胤などに引き継がれていきました。
そして平田篤胤の思想は、幕末そして明治維新における尊王攘夷運動の思想的支柱にもなっていきます。
そしてやがてこの流れは、明治における神仏分離(神道と仏教、神社と寺院をはっきりと区別すること)や廃仏毀釈(仏教の排斥運動)へとつながり、ついには仏像や仏具の破壊運動にまで発展してしまいます。こういったことが実際に起きたこともここに併せて記しておきます。
理屈や作為に偏らない素直な心を重視した国学者たちの精神と、この過激な運動とがどう結びついてしまったのか、そこに至る経緯については、自分は勉強不足で無知であるため、今後このような点については調べていきたいと考えています。
賀茂真淵の著作
賀茂真淵の業績は、とくに「万葉集」の研究で高く評価されており、その成果は「万葉考」「万葉集遠江歌考」「万葉解」「冠辞考」にまとめられています。
その他、代表作としては「五意考」と呼ばれる以下5つの書、
・「歌意考」(古歌に関する書)
・「文意考」(古文に関する書)
・「語意考」(古語に関する書)
・「書意考」(古書に関する書)
・「国意考」(日本の精神に関する書)
などがよく知られており、日本古来の精神の重要性を説き、国学の基礎を築いたことから、荷田春満、本居宣長、平田篤胤らとともに「国学の四大人」に挙げられています。
今現在の日本をも評している賀茂真淵の指摘
今回自分が賀茂真淵の思想に焦点をあてて記事を書こうと思った理由は、彼が著作の中で指摘していることが、そのまま今現在の日本に当てはまるものであると感じたからです。
前記見出し「賀茂真淵の思想」の章にある彼の主張の要点において、
・「現在の中国にあたる地域」⇒「米国」
・「儒者」⇒「近代経済学、近代医学、近代経営学などの米国発信の最新学問を尊ぶ学者や知識人」
と読み替えると、今現在日本で広く見られる現象と完全に重なると感じたからでした。
日本はこれまで明治以降、急速に近代化・西洋化を進め、古いものを捨て去り最先端の生活様式を獲得することが良いこととされ、先進国である欧米、中でも戦後はとくに米国式の考え方や社会システムを一つのロールモデルとして捉え、西洋(とくに米国)的な考え方で日本の社会を変革してきたように見受けられます。
その結果、社会はたいへん複雑になり、専門化も急速に進んだ上、日本人の価値観とは本来相容れない考え方を社会システムや規則に組み込むようになって、課題の本質や我々にとっての理想のかたちが非常に分かりにくく見えにくい社会となってしまったように思います。
250年以上も前にこの世を生きた日本人が指摘したように、あまり理屈ばかりに偏ることなく、現実をもっと素直に見て、過去の長い歴史の中で得た経験も参考にしながら、社会全体を我々の価値観に合う調和した社会に導くことが今こそ必要とされているように感じるのです。
このような劇的な社会環境の変化の中に身を置いていながら、歴史を振り返れば日本人の本質は近代化する前から何も変わっていないのだということを、この度賀茂真淵の主張によって気付かされました。
進化しているというのは錯覚であって、先人に学んで「我々日本人とは本来どういう者であるのか?」ということを今一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。
賀茂真淵が指摘している通り、日本古来の精神に備わっていた「純直な心」「和らぎの心」を今こそ改めて見直し、取り戻すべき時なのかもしれません…。
出典及び参考資料
1) 賀茂真淵, 「国意考」, 大日本思想全集 第9巻, 大日本思想全集刊行会, 1933
2) 賀茂真淵, 「歌意考」(校注・訳 藤平春男), 新編日本古典文学全集87 歌論集, 小学館, 2002
3) 賀茂真淵記念館【浜松生まれの国学者、賀茂真淵】
4) 賀茂真淵 – Wikipedia
5) 本居宣長 – Wikipedia
6) 冠辞考 – Wikipedia
7) 日本の儒教 – Wikipedia
8) 国学 – Wikipedia