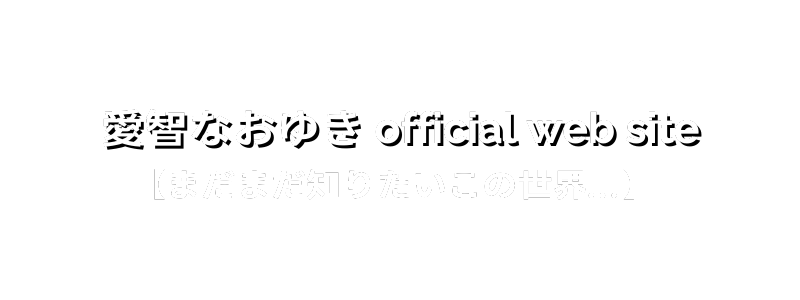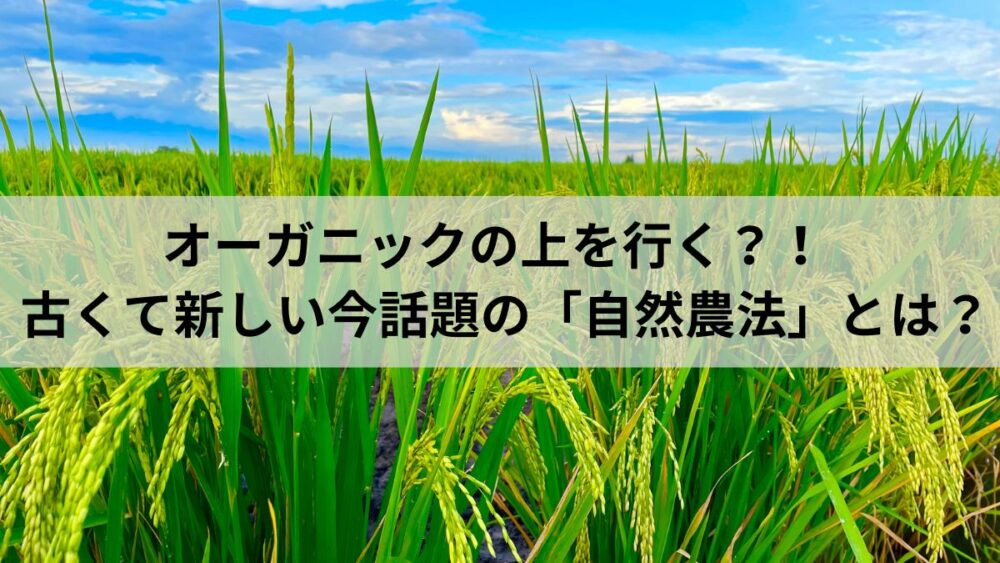現在世界的に注目を集めているこの方をご存じだろうか?

お名前は今橋伸也さん。なんと、無肥料・無農薬の自然農法をイギリスで約20年続けており、40種類以上もの野菜を自然農法で栽培し続けている農場従事者である。現在はこの自然農法を世界に普及させる活動をするYouTuberでもある。
近年、人の健康にも環境にも良い野菜といえば「オーガニック野菜」とよく言われている。オーガニック農法(有機農法)は、化学物質を一切使用せず大変きびしい基準をクリヤーして栽培したものだけが認証を受けられるものだが、それでも、化学肥料の代わりに有機肥料を使用する。
これに対し、自然農法は肥料を全く使わない。「肥料を使わないのになぜ野菜ができるの?」と不思議に思う方も多いかもしれないが、実際に野菜が収穫できているのである。
最近このことを知り大変衝撃を受けたのだが、先日2025年2月25日茨城県において今橋伸也さんのセミナーが行われることを知り、早速申し込んで参加をさせていただいた。
今回の記事では、この自然の力を活かした自然農法の概要(主にオーガニック農法との違いについて)並びに、これまで精力的に活動をされている今橋さんの経歴などについてごくごく一部ではあるがご紹介をさせていただきたい。
自然農法とオーガニック農法とは何が違う?
自分もそうなのだが、まずここで普段あまり農業との関わりがなく、農法についての知識があまり無い方のために、自然農法とオーガニック農法の違いをわかりやすく示すことにする。20年以上もの間、自然農法を続けている今橋さんがイギリスでの状況を踏まえこれらの説明をしているので、そちらを参考とした。
(尚、イギリスは農産物に関して、オーガニック認証の相互承認(他国の認定結果などが自国のものと同等であることをお互いに認めること)を日本と交わしている。)
自然農法とオーガニック農法との大きな違いは、自然農法では肥料を使用しないのに対し、オーガニック農法では化学肥料でない有機肥料を使用するということである。オーガニック農法では肥料を使うことが野菜作りの前提となっている。
これに対し、自然農法では天然のものであっても動物のフンや卵の殻、籾殻などを使用しない。本来土が自然の状態にある状況から大きく逸脱すると思われることを自然農法では基本的にやらないのである。
一番驚くことは、自然農法で無肥料で育てても、状況によってはオーガニック農法の数十倍の収穫ができたということだ。肥料を人工的に与えなくても、植物は光合成により自らエネルギーを作り出し、また本来自然の状態の土の中にいる微生物が関与する働きによって、必要な栄養分を賄っていると考えられている。これらのことは現在、最新科学をもってしてもまだ十分には解明されていない。
そして次に自然農法に使用する「種」。今橋さんは遺伝子組換え品やF1品種のものは使用せず、自然農法で育てた農作物から自家採取をして使っている。
今橋さんによると、自家採取した種にはすばらしい力、それが植えられた場所(自然環境)への適応力があるそうだ。毎年変動する気温、気候、降水量などの自然条件に適応して育ち続け、収穫まで迎える生命力があるということなのだろう。
ときには、アブラムシなどの害虫の被害にあったり、植物が病気になることもあるそうだが、今橋さんはそのような場合にも一切農薬は使わない。
ある年買ってきたそら豆の種を植えたら黒いアブラムシが大量に発生した。そのときも自然の力を信じ、これといって特に対策をしなかったが、枯れずになんとか種はつけた。翌年、またその翌年と種の自家採取を自然農法で続けたところ、5年を過ぎる頃からアブラムシがわかなくなったというのだ。自家採取によって命を繋いだ種は、どんどんその生命力を増し、健康で強く、環境に順応できる野菜を作るようになったのである。
さらに興味深いこととして、イギリスでは連作しているものはオーガニック認証がされない、ということがある。そもそも通常、慣行農法やオーガニック農法では、(品種による違いはあるが)連作障害が出やすく、連作で収穫をするのが難しい。
その一方、今橋さんが取り組んでいる自然農法では、連作しても問題なく野菜が収穫されている。オーガニックの世界ではとくに連作が不可能とも言われているケールまで、今橋さんの農場では毎年連作で収穫が出来ているから見学にくる農業関係者はみな驚いている。
厳しい審査がされているイギリスにおいて、通常は連作したものはオーガニック認証されないのであるが、自然農法で連作された今橋さんの農場の農産物は、例外的に特例として「オーガニック認証」を受けることができた。
このように自然農法とオーガニック農法ではいくつかの違いがあるのだが、それらを簡単に表にまとめてみた。以下参考になれば幸いである。
| 自然農法 | オーガニック農法(有機農法) | |
| 目的 | 食する人の健康増進と 地球環境の良化 | 同左 |
| 基本的な考え方 | 土の本来の力を引き出す | 人工的なものではなく天然由来のもので土の栄養素を調整する |
| 農薬 | 不使用 | 化学農薬は不使用 |
| 肥料a) | 不使用 | (動物のフンなどの) 有機肥料は使用可 |
| 堆肥b) | 自然堆肥c)は使用可 | 有機堆肥は使用可 |
| 海藻、貝殻、卵の殻、籾殻など | 不使用 | オーガニックであれば 使用可 |
| 種 | 自家採取を推奨 遺伝子組換え品やF1品種は不可 | オーガニックであれば F1品種d)も使用可 |
| 連作 | 可 | 不可 |
| 輪作 | 可 | 推奨 |
| 耕起e) | してもしなくてもよい | 同左 |
a) 肥料:植物を育てるために施される栄養成分のこと。
b) 堆肥:土壌改良を主な目的として作られた、微生物による有機物質(落ち葉、籾殻、生ゴミ、動物のフンなど)の分解物。
c) 自然堆肥:100%自然なもので作られた堆肥。例えば、無肥料・無農薬の土地で育った草、自然農法で栽培した野菜など。動物のフンなどは不可。
d) F1品種:雑種第一代のこと。異なる2つの系統の交配により生まれた第一世代目の子孫。一般には、その一世代に限って安定して一定の収量が得られる。
耕起:耕すこと。
今橋さんが自然農法を始めたきっかけとイギリスへの渡航
ここで今橋伸也さんのこれまでの経歴について簡単に触れることにする。
親が農家でもなく、とくに農業に関わることなく大学を卒業した今橋さん。就職活動のときに「このまま就職してもいいのだろうか?」とふと疑問が湧く瞬間があった。これまでとくに夢ややりたいこともなく普通に生きてきた。
「このままでいいのか?」そして時は過ぎ、結局、内定が決まっていた会社にも、他のどこにも就職せず、そのまま大学卒業を迎えることになる。
大学卒業後に家の近くで自然農法をしている人(友人の知り合い)がいた。そこで農業に興味を持った今橋さんは、アルバイトをしながら2畝(1畝=約99m2。10畝=1反)の畑で夏野菜の栽培を始める。
ある時、自然農法に取り組んでいる知人から、「地球環境」に関する講演会への誘いを受ける。特別、地球環境に関心がなかった今橋さんであったが、その知り合いの強い誘いもあり、その講演会を聴きに行くことになった。
ところが、その講演会の内容が当時の今橋さんにとっては衝撃的だった。「このままでは地球が滅ぶ。自分も何か行動を起こさなければ…」という強い衝動に駆られた。それは今橋さんにとって初めての経験だった。
そのとき考えたのは「この地球環境を変えるために自分が出来る唯一のことは自然農法だけ。それならこれを本気でやってみよう。たった2畝の畑ではなく、もっと大きい畑でやらなければ」ということ。
それから農場探しを始めたが、出身地の福岡県では見つからず、家から遠い山口県で農地が見つかった。そして水田と畑を借り、その農場の近くに住むことになる。
農業経験がほぼゼロで、慣行農法でもなく、いきなり自然農法に挑戦することになった。始めた当初は食べるものに困るほどお金が無く、体重も減って痩せこけてしまうほどだったが、それでも僅か数人の友人が応援をしてくれて、週末には手伝いにも来てくれた。それが心の支えとなって自然農法を続けることができた。
そしてその後、水田に田植えをしたときに驚くべき経験をすることになる。
お金もないので機械も買えず手で田植えをしたのだが、なんと水田に植えた苗が1週間も経たないうちに一斉に枯れ出したのだ。あわててプロの農家の人に見てもらったのだが、その人も「こんなひどいのは見たことが無い」という始末。何をすればいいのやら途方に暮れていたが、そのときふと思いついたことがあった。
その頃今橋さんは人間関係など色々悩みが多く、不満と怒りの心で田植えの作業を行っていたことを思い出した。
「もしかするとその怒りの心、人の心がこの苗に伝わったのではないか?もしそうならば、今度は感謝の心、清らかな心で植物に接すれば、それも伝わるのではないだろうか?」
今橋さんはそう考え、早速そのような気持ちで真摯にそのお米の苗に向き合い農作業をするようにした。すると驚くべきことに、枯れかけていた苗から新葉が出るようになり見事復活したというのだ!そしてその一度枯れかけた苗が、秋には見事収穫できるまでになったのである!
その時の収量量は、水田1反あたり8俵(米1俵は60㎏に相当)。当時農薬を使う現代の慣行農法の平均収量が1反あたり8~10俵だったというから、初心者が初めて取り組んだ自然農法の米作りで、なんと農薬を使用した慣行農法と同等の収穫を得たのである。
自然の力のすごさに驚愕した今橋さんは、翌年、今度は最初から穏やかな心でお米の苗に接し、米作りに取り組むようになった。その結果、2年目は1反あたりなんと12俵もの収穫があり、農薬を使用する慣行農法による収穫量をはるかに上回ったのである。
「それまで農業について殆ど知識がない初心者だったから、なんの躊躇もなく自然農法を続けることができた」と今振り返る今橋さん。
2年間山口県で自然農法に取り組んだあとは、こんなすばらしい自然農法を世界に広めたい、そういう思いを抱くようになる。そしてその後3年間の準備期間を経て、たまたま知り合いがいた英国へと渡ることになる。
「自然農法」による常識破りの収穫量に世界が驚愕!
英国に渡った今橋さん、最初はロンドンの市民農園、7畝の小さい農場で自然農法を始めた。その農地で英国でも自然農法で野菜ができることを実証し自信を深めた今橋さんは、もっと大きい農地を探すようになる。
ロンドンの北、エセックスに5反の農地が見つかりその後そちらに移ることになるが、その農地が空いていた理由は、土が粘土質で野菜が育たないからだった。
「こんな場所で野菜はできない」と現地の人にバカにされたが、半年後には野菜がどんどん収穫されるのを見て、現地の人も謝ったという。
さらにその後は、イェーツベリーに移り、2ヘクタール(1ヘクタール=10,000m2)の農場で自然農法を続けた。
イェーツベリーに移ってからも、トマト、じゃがいも、にんにく、ニンジンなど、ありとあらゆる様々な種類の野菜を育てているが、この地ではさらにぶどう栽培に挑戦する。
ヨーロッパと言えばぶどうの産地のイメージがあるが、ぶどうが多くとれるのは、イタリア、スペイン、フランスなど、比較的温暖な気候で乾燥した地域。日照時間も長いところの方がぶどう栽培には適している。つまり寒すぎるイギリスはぶどう栽培には向いていないのだ。
実際、イェーツベリーの農場周辺でもぶどう農家はほとんどいない。その地で自然農法によるぶどう栽培にチャレンジした。
今橋さんがぶどうの産地スペインのオーガニック農家に収穫量を聞いてみたところ、ぶどうの木1本あたり500g~1㎏のぶどうがとれるそうだ。
一方、自然農法を10年以上継続した今橋さんの農場では、ぶどうの木1本につき、なんと26kgを超える収穫量が確認された。上記スペインのオーガニック農法の平均収穫量を750gとすれば、なんと約35倍の収穫量である!
しかも、今橋さんはぶどう栽培についてはほとんど勉強をせず、自分の感覚をたよりに栽培を続けており、おまけに最初に植えたぶどうの苗は、品種にもとくにこだわらず、eBayというECサイトで一番安い苗を購入したというから、さらに驚きである。
このような常識破りの農法とその成果は、イギリスで大変注目を集め、農業雑誌や業界新聞などに取り上げられるようになる。
そして、2019年には英国全国ネットBBCラジオ4で独占インタビューを受け、2022年には、世界最古の日刊新聞「タイムズ(The Times)」の日曜版「サンデー・タイムズ(The Sunday Times)」に取り上げられた。
また、世界最大の有機農業イベント「オックスフォード・リアル・ファーミング・コンファレンス」では4年連続講演者として発表をしている。
このすばらしい農法を世界中に広げるため、現在今橋さんはイギリス以外にも、アイルランド、ギリシャ、スペイン、ドイツ、フランス、イタリアの自然農法アドバイザーを務め、更にはYouTubeを通じて世界に向けて、その20年以上にもわたり培ったノウハウを惜しむことなく発信し続けているのである。
引用元:YouTubeチャンネル「自然栽培実施20年のノウハウ教えます」
そしてついに2024年の秋からはいよいよ日本に帰ってきた。高知県で農場を探し自然農法を行うことを決めたのである。
これまでの常識を根底から覆している今橋さんの「自然農法」。その秘訣は以下の3つにあるという。
1)無肥料、無農薬で土をきれいにする
2)自然農法で自家採取した種を使う
3)土と野菜、自然に対して感謝の心で接する
今世界が注目しているこの「自然農法」。この農法が当たり前となる日もそう遠くはないのかもしれない…。
出典及び参考資料
1) 自然栽培実施20年のノウハウ教えます – YouTube
2) 今橋伸也, 自然農法ラーニングプログラム Part 3, 2025/02/25
3) 有機食品の検査認証制度:農林水産省
4) 有機栽培に農薬が使われている!?「有機JASマーク」の盲点をしっかり知ろう | 農業とITの未来メディア「SMART AGRI(スマートアグリ)」
5) 肥料 – Wikipedia
6) 堆肥 – Wikipedia
7) 雑種第一代 – Wikipedia
8) サンデー・タイムズ – Wikipedia
9) タイムズ – Wikipedia